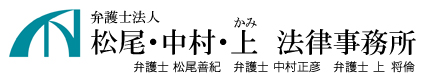交通事故
交通事故について
交通事故の被害に遭ったときの問題の多くは、加害者自身あるいは加害者側の保険会社の理不尽な対応です。
交通事故の被害に遭っただけでもつらいのに、どちらが被害者なのかわからないような誠意のない加害者の対応、足下をみた低い示談金の提示や一方的な治療費や休業損害の支払の打ち切りなどの保険会社の不誠実な対応に苦しめられることは少なくありません。
交通事故被害者は2度被害に遭うといわれる所以です。
当事務所では、交通事故被害者救済の観点から、被害者側のご相談は、初回相談料1時間無料で対応しています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
被害者、ご家族、ご遺族の方々の思いをしっかりと受けとめ、少しでもお心が休まりますよう、私たちは闘っています。
もし交通事故に遭ったら
もし交通事故に遭ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。
警察に通報するなどすべきことがいくつかありますが、この点については、国土交通省の自賠責保険(共済)ポータルサイト「交通事故にあったらまずどうする」に詳しく記載されていますので、こちらを参照されるとよいでしょう。→国土交通省自賠責保険(共済)ポータルサイトへ
上記リンク記載事項以外に加えてなすべきこととしては、自賠責保険の外に、任意に加入されている自動車保険会社へ連絡し、事故の報告をするとともに、対応について指示を仰ぐことが挙げられます。
他方、交通事故時の対応として、やってはいけないことは、「損害は賠償するから警察への通報をしないで欲しい」「違反点数が累積していて、免停・免取になってしまう」などと言われて、相手方に上手く言いくるめられてしまったり、変に同情してしまい、
○警察に通報しない
○相手方の身分証明を確認しない
ことであり、上記の内、とりわけ警察への通報をしなかった場合、確認した相手方の氏名や連絡先などが虚偽であり、連絡がとれないであるとか、連絡がとれたとしても、とぼけられてしまうなどすると、手の打ちようがない事態に陥ってしまうことになりかねませんので、くれぐれもご注意ください。
また、事故当時に自覚症状がないために、自分の身体を過信してしまい、
○病院へ行かない
ことも適切な対応ではありません。
場合によっては、命にかかわるような脳や内臓の損傷などであっても、自覚症状がすぐに現れないこともありますので、過信は禁物です。
また、事故後日数が経過した後に病院で診断を受け、後遺症があることが判明した場合、相手方から、その症状は交通事故が原因ではないと主張され、争いになるおそれがあります。
交通事故に遭ったら、速やかに医師の診断を受け、領収書類はタクシー代など病院への交通費の領収書も含めて大切に保管しましょう(電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は領収書がなくとも正当な交通費として認められます)。
自動車保険の弁護士費用特約の有無を確認しましょう
♦弁護士費用特約とは
弁護士費用特約(「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用等補償特約」など保険会社によって名称は異なります)とは、保険に付加することができる特約で、偶発的な事故による被害について弁護士に相談した場合や、加害者側への損害賠償請求を依頼した場合の弁護士費用等を保険会社が支払ってくれるというものです。
交通事故被害に対する補償の一環として、主要な自動車保険の大半で取り扱われているほか、一部傷害保険、火災総合保険、総合損害保険などにおいても取り扱いがあります。
1年間の特約保険料は、概ね1500円~2000円程度と比較的安価ですが、1回の事故について被保険者1名あたりの弁護士費用は300万円まで、法律相談費用も10万円まで補償してもらえるのが一般的で、被害者に一定の過失があっても、相手方に損害賠償請求をする場合であれば使用することができます。
また、以下のように記名被保険者(保険証券の被保険者欄に記載されている人)以外の人の分の弁護士費用等についても支払ってもらうことができるのが大きな特徴となっていますので、契約の範囲外だと自己判断する前に、保険会社もしくは私たち弁護士にご相談ください。
♦弁護士費用特約で補償されうる人
弁護士費用特約において補償の対象となる被保険者は、概ね以下のとおりですが、その範囲は、保険会社により異なります。
実際に被保険者となりうるかは、当該自動車保険の約款などにより、ご確認ください。
- ① 記名被保険者
- ② 記名被保険者の配偶者
- ③ 記名被保険者またはその配偶者の「同居の」親族
- ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の「未婚の」子
- ⑤ ①~④以外の者で、「被保険自動車の」同乗者
- ⑥ ①~④以外の者で、「①~④に該当する者が運転者として運転中の」被保険自動車以外の自動車の同乗者
- ⑦ ①~⑥以外の者で、「被保険自動車」の所有者
- ⑧ ①~⑦以外の者で、「①~④に該当する者が運転者として運転中の」被保険自動車以外の自動車の所有者
①~⑤については、ほぼ全ての保険会社で被保険者となっており、⑦についても多くの保険会社では被保険者としていますが、⑥、⑧まで被保険者としている保険会社は少ないようです。
♦弁護士費用特約の確認の手順
交通事故被害に遭われた場合、以下の保険について、弁護士費用特約の有無を確認してみてください。
保険証券や約款などの記載から判然としない場合は、当該保険会社へ電話して確認するとよいでしょう。
- ① 被害者自身が加入している自動車保険
- ② 被害者の配偶者や同居の親族が加入している自動車保険
- ③ 被害者が未婚の場合、その親が加入している自動車保険
- ④ 被害者が自動車に搭乗中に被害に遭った場合、その自動車を被保険自動車とする自動車保険・その自動車の運転者やその配偶者、同居の親族(運転者が未婚の場合、その別居の親も含む)が加入している自動車保険
- ⑤ ①~④に該当する者が加入している傷害保険、火災総合保険、総合損害保険等
弁護士費用特約が利用可能である場合、自ら弁護士を探して、弁護士費用特約を利用して依頼するほか、当該保険が日本弁護士連合会と協定を締結している保険会社のものであれば、保険会社から弁護士会へ弁護士紹介の依頼をしてもらうこともできます。
弊所では、交通事故被害に関するご相談は、初回相談料1時間無料で対応しておりますので、ご不明なようでしたら、ご活用ください。
弁護士費用特約の利用が可能か、弁護士が診断いたします。
被害補償の手続
交通事故の被害に遭った場合、どこへどのような請求をしていけばよいのでしょうか。
この点、被害の程度や過失割合、加害者、被害者双方の保険加入状況などにより、とるべき手続や手続の順序が異なってくるなど、なかなか複雑です。
そこで、以下では概要にとどめ、おさえておきたいポイントをご説明いたします。
♦自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険とは、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられている、いわゆる強制保険で、交通事故により死傷した被害者の救済を目的とした損害保険です。
ポイント
○物損は補償されない
「死傷した」被害者の救済を目的としているため、物損(自動車の修理代など)は補償の対象になりません。
○自賠責保険における被害者は死傷した人
実際に死傷した人の方が、過失(落ち度)の割合が大きかったとしても、被害者として補償を求めることができます。
○過失相殺はされないが、重過失があった場合、減額される。
後述の任意保険における補償の場合、過失相殺といって、過失割合に応じて厳密に保険金が減額されますが、自賠責保険の場合、被害者に重過失(過失割合が70%を超える場合)がある場合にはじめて保険金が減額されます。
○加害者でも請求できる
例えば双方ともにケガをしたが、相手方のケガの方が重傷であったため、その損害を立て替えて支払った場合、審査の結果、認められれば、保険金の支払を受けることができます。
○政府保障事業~ひき逃げや加害者が自賠責保険にすら加入していない場合の救済
ひき逃げ事故に遭ってしまった場合には、加害自動車の保有者が明らかでないため、損害賠償の請求をすることができないことから、自賠責保険の対象となりません。
加害者が自賠責保険に加入していない場合についても、無保険であるわけですから、同様に自賠責保険の対象外となります。
このような「ひき逃げ事故」、「無保険事故」に遭った被害者については、政府保障事業という制度により救済が図られています(自動車損害賠償保障法第72条)。
制度の詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済)ポータルサイト「相手が自賠責保険(共済)に入ってなかったら?」「ひき逃げ事故にあったら?」をご参照ください。→国土交通省自賠責保険(共済)ポータルサイトへ
♦任意保険
任意保険とは、任意に加入する自動車保険のことで、補償の範囲は、加害者が加入している保険の契約内容により異なりますが、交通事故被害者の観点から見ると、自賠責保険では補償されない部分を補償してくれるものといえます。
自賠責保険とは異なり、厳密に過失相殺がなされ、保険金額が減額されます。
また、契約の内容によっては、被害者自身が加入している任意保険からも補償を受けることができる場合があります。
ポイント
○保険会社との示談交渉
ご自身で保険会社との交渉をする場合、当然、相手方保険会社は専門の部署で対応してきますので、専門家vs素人といった様相を呈するため、そもそも大きなハンデを背負っていると考えた方がよいでしょう。
そして、相手方保険会社はあくまで自社の利益のために行動するのであって、被害者のために行動するものではないということを頭に入れておくべきです。
被害者側に弁護士が就いていない場合、相手方保険会社が被害者側に示談案として提示してくる賠償金額は、裁判上認められる水準を大きく下回っているのがむしろ一般的なのです。
とりわけ後遺障害がある場合、賠償額が大きく変動する可能性が高いため、無料の法律相談を利用するなどして、弁護士に相談することをお勧めします。
○弁護士費用特約
保険会社との交渉を自分でするのは面倒だが、弁護士費用をかけてまで…というような場合、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認してみましょう。
弁護士費用特約がついている場合、その適用の条件を満たしていれば、弁護士費用をご自身が加入している保険会社が支払ってくれます(1回の事故につき1名あたり300万円を上限としているのが一般的です)。
これにより、保険会社との面倒な交渉や訴訟を弁護士に依頼することができ、かつ経済的な負担も発生しない(あるいは大きく軽減される)、補償の基準も弁護士基準となり、補償金額が上がるケースが多いため、交通事故被害者にとって大変心強い特約といえます。
また、弁護士費用特約はその適用の範囲が広く、同乗者にも別途適用されますし(例えば被害車両に乗っておられた方3名が負傷した場合、3名合計で上限300万円ではなく、1人ずつ、それぞれが300万円までの弁護士費用を負担してもらえます)、別居の子供が交通事故に遭った場合や、交通事故以外の日常の事故(物損含む)にも適用されるケースもありますので、もしご自身の保険に弁護士費用特約がついているのであれば、契約の範囲外だと自己判断せずに、一度加入している保険会社に確認してみられるとよいでしょう。
♦労災保険・健康保険
交通事故被害による「負傷、疾病、障害又は死亡」が、「業務上の」ものである、または「通勤による」際のものであると認められる場合、労災保険から様々な給付を受けることができます。
労災保険は健康保険とは異なり、自己負担分がなく、過失相殺もされません。
また、自賠責や任意保険から既に補償を受けていたとしても、減額調整されず、満額支給される特別支給金というものがあり、支給要件に該当する場合、別途支給を受けることができます。
一方、健康保険は、労災保険が適用されない場合に使うことができます。
交通事故の場合、健康保険は使えないというのは誤りです(ただし所定の手続が必要)。
むしろ、加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者が任意保険に加入していたとしても被害者側にも過失があるような場合には、健康保険を利用した方が有利となります(自賠責保険の保険金額を温存したり、過失相殺の金額を低く抑えることにより、より多くの損害をカバーすることができる)ので、これらのケースに該当する場合、被害者であっても、積極的に自己の健康保険を利用すべきであるということになります。
これは、労災保険の適用がある場合も同様です。
健康保険も労災保険と同様に過失相殺はされませんが、病気で病院にかかる場合と同様に3割は自己負担となります。
ポイント
○事業主・会社が労災保険料の支払をしていない場合でも請求できる
たとえ、事業主・会社が労働保険の加入手続を怠り、労災保険料を支払っていない場合でも、「労災」に該当する以上は、被害者自身が労働基準監督署に申告することにより、救済を受けることができます。
ただし、労働保険の加入手続すらしていないような悪質な事業主・会社の場合、労災保険を利用することにより、その後の雇用関係についてのトラブルへと発展する可能性が高いため、このようなケースでは、事後の対応も含めて弁護士にご相談ください。
○示談は慎重に
示談書の内容によっては、示談以降は労災保険や健康保険を使用しての治療を受けることができなくなるおそれもあります。
ご自身で示談をされる場合には、とりわけ示談後の治療費の負担方法について、どのような記載となっているかをよく確認しましょう。
示談は非常に重大な局面ですので、示談前に、専門家である私たち弁護士に示談書の内容確認をご依頼いただく方がよいでしょう。
♦加害者に対する直接請求
自賠責保険による補償の上限を上回る損害が発生しているにもかかわらず、加害者が任意保険に加入していないような場合、加害者へ直接請求していくことになります。
まずは、示談による解決を試みることになります。
示談がまとまらない場合、裁判を検討することになりますが、相手方の支払意思や差押可能な財産があるのかといった回収可能性や、費用対効果を検討した上で、最終的な判断をすることになります。
治療費や休業損害の打ち切りにあったら
むち打ちなど自覚症状のみの場合、一定期間の経過をもって、保険会社は半ば自動的に治療費などの支払の打ち切りを通告してきます。
保険会社は、これら支払の打ち切りをもって、症状固定へもっていきたいと考えています。
症状固定と認定されると、交通事故損害賠償上の治療期間は終了となるため、保険会社は、以降の通院治療費を賠償する必要がなくなるからです(症状固定に達した後、なお残存している傷害の症状(後遺症)については、後遺障害として別途慰謝料等の損害賠償を求めていくことになります)。
症状固定とは、傷害の症状が安定し、医学上一般的に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなった状態をいいます。
つまり、これ以上治療を続けても、被害者の方が受けた傷害が回復しない状態になると症状固定と認定されるわけですが、ここで肝心なのは、症状固定はあくまで被害者自身と医師との相談の結果、判断されるものであり、保険会社が決めるものではないということです。
したがって、治療費などの支払の打ち切りによって、保険会社から圧力をかけられたとしても、医師が依然として治療が必要であると判断している以上は、真に症状固定となるまで治療を継続します。
支払を打ち切られてしまった後の治療費などは一旦自己負担となりますが、これら自己負担をした部分は、後日の保険会社に対する請求において、あわせて補償を求めていきます。
治療費や休業損害の支払を打ち切られてお困りのようでしたら、あきらめてしまわずに私たちにご相談ください。
解決事例
交通事故被害によって、脳脊髄液減少症を発症したとして、治療を受けていた交通事故被害者の損害賠償請求について、加害者側保険会社が同症状の発症自体を否定し、治療費の支払などを拒絶していた事案において、提訴し、主治医の協力を得て症状等を明らかにするなどして、同症状が生じていることを主張・立証した結果、裁判所より、少なくとも同症状の疑いがあることは否定できないとして和解勧告があり、その治療費や治療期間に相当する慰謝料を前提とする和解が成立した事例。
後遺症について-後遺障害の等級認定を見直してもらうには
症状固定に達した後、なお後遺障害が残っている場合、相手方任意保険会社または被害者自身が、後遺障害等級の認定申請を行い、審査の結果認定された等級に基づいて補償を受けるわけですが、この等級が何級になるのかによって、補償金額が大きく異なってきます。
しかしながら、必ずしも被害者の方にとって、妥当な、納得できる等級が認定されるわけではありません。
場合によっては、非該当といって、そもそも後遺障害にあたらないと判定されてしまうことさえあります。
このように認定された等級、あるいは非該当と認定された結果について、不服がある場合、異議申立という手続によって、認定のやり直しを求めていくことになります。
異議申立は、審査結果を見直すに足りる新たな書面を提出しなければ、結果が変わることはありませんが、専門家である私たち弁護士が症状についての説明を補ったり、わずかな診断書の記載漏れを医師にあらためてもらうことによって、等級や非該当の結果が見直されるケースもあります。
また、他覚所見のない(本人の自覚症状しかない)むち打ちのケースであっても、後遺障害と認定されることもあります。
正しい認定がされているかどうか、少しでも疑問に思われるようでしたら、一度ご相談ください。
よくあるご質問(交通事故Q&A)
- Q
- 主婦であっても休業損害は認められるのでしょうか?
- A
-
主婦については、最高裁の判例において、「家事労働によって現実に金銭収入を得ることはないが(中略)家事労働は財産上の利益を生ずるものというべき」であるとの判断が示されていますので、受傷のため家事に従事することができなかった期間についての休業損害が当然に認められます。
具体的には、統計による女性の平均賃金相当額をもとにして算定された金額が、主婦の方の休業損害として補償されます。
パートなどにより他の収入がある主婦の方の場合は、平均賃金相当額をもとに算定された金額と、パート等の収入をもとに算定された金額とを比較して、より高い方の金額が休業損害として補償されます。
休業損害の具体的な金額については、個別具体的事情により異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
- Q
- 無職であっても休業損害は認められるのでしょうか?
- A
-
交通事故受傷時、無職であった場合、休業損害が一切認められないというのは誤解です。
確かに、休業損害とは、交通事故被害に遭うことによって、休業したがために減ってしまった収入部分を補償するものである以上、収入がない無職の場合、休業損害を観念しえないため、認められないのが原則です。
しかし、被害者に労働能力や労働意欲があり、就労の可能性もあったような場合には、たとえ事故受傷時に無職であったとしても休業損害が認められるケースがあるのです。
実際に休業損害が認められるか否かは、個別具体的事情の検討が必要となりますので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
- Q
- 自営業をしているのですが、確定申告において過少申告をしている場合、実際の収入を基礎とした休業損害を受けることはできないのでしょうか?
- A
-
通帳や帳簿等によって、申告していた所得以上に所得があったと証明することができれば、実際の所得金額を基礎として算定された休業損害金の支払を受けることができますが、この立証は相当な困難を伴うものです。
そもそも確定申告において、過少に申告をするという不正な行為をしてしまったわけですから、不利益な取り扱いを受けることがあったとしてもやむを得ない面があるとご理解ください。
- Q
- 裁判になった場合、終わるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- A
-
裁判の期間については、よくご質問をいただくのですが、事案により大きく異なりますし、相手方の対応次第で状況は刻々と変わっていくものでもあるため、実際に裁判をする前にお答えすることは大変難しいということを、まずご理解ください。
あえて申し上げるとすれば、交通事故裁判については、経験上、提訴から1年~1年半で解決するケースが比較的多く見受けられます。
- Q
- 加害者に対する請求権や自賠責保険への請求権も時効によって消滅してしまうことがあるのでしょうか?
- A
-
♦加害者に対する請求権について
加害者に対する請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権にあたりますので、民法第724条により「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から」3年で時効となります。
したがって、加害者が判明している場合、損害項目によっては、その損害が発生したときから3年で請求できなくなってしまいます。♦自賠責保険への請求権について
自賠責保険の被害者請求については、加害者に対する損害賠償請求権と同じく、傷害、死亡についての損害賠償請求権は事故時から3年、後遺症についての損害賠償請求権は症状固定時から3年で時効になります(ただし平成22年4月1日以降に発生した事故の場合。自動車損害賠償保障法第19条、4条及び平成20年法律第57号保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第15条、16条)。
♦弁護士へのご相談を
時効については、時効の中断といって、今まで進行していた時効期間がリセットされてゼロに戻り、新たに時効期間をカウントし始める制度(民法第147条、157条)や、いつから時効の進行が始まるのかという起算点の問題など、正確な専門的法律知識及び実務経験が要求される場面であるため、時効についてお悩みの場合は、法律の専門家である弁護士にご相談される方がよいでしょう。